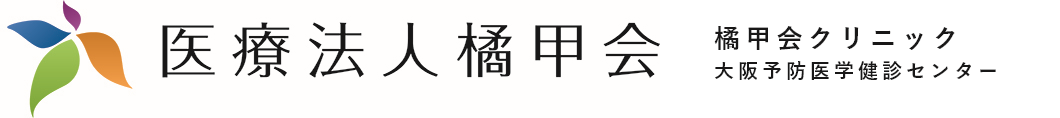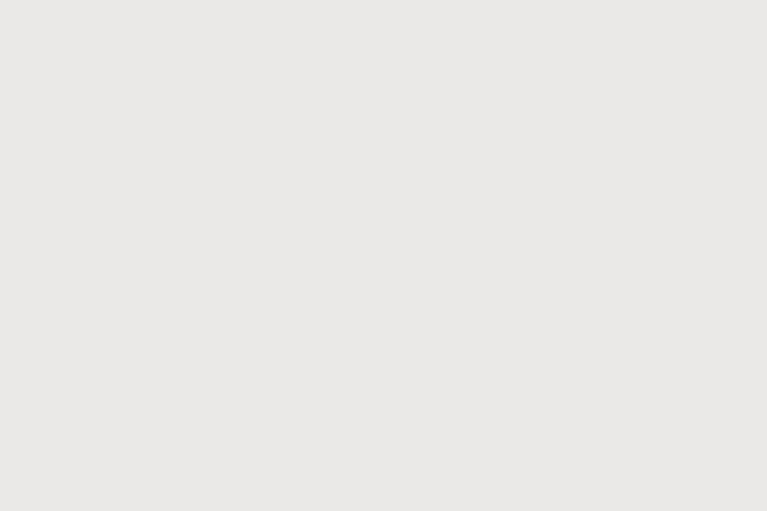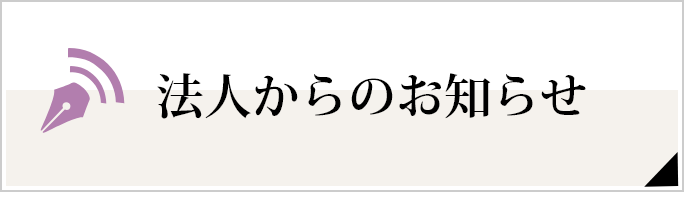初めまして。
こちらにてブログを更新します。 よろしくお願いします。
2014.05.09
心臓の刺激伝導系と心拍動
心臓が拍動するには、1回ごとに刺激が必要です。その刺激を発生する部位が洞結節で、上大静脈が右心房に開口する部位にあります。そこから出た刺激が周囲に波状に広がって、左右の心房を収縮させます。その刺激は、同時に、心房内刺激伝 […]
2014.05.08
心電図検査
心電図検査は心臓の活動に伴って発生する微弱な電流を記録したもので、心臓の状態をみる上で不可欠な検査です。 心電図検査では、心臓の活動電流の取り出し方を誘導法といいます。最も基本的な誘導法は、手足から誘導するⅠ誘導、Ⅱ誘 […]
2014.05.08
心臓病調査票
心臓病調査票は、心電図検査と共に心臓病の抽出手段として極めて重要です。例えば、川崎病やリウマチ熱の既往があると心臓に後遺症が残っている可能性があります。また、頻拍発作や失神の既往は、その時に危険な不整脈が起こっていた可能 […]
2014.05.08
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
ARCHIVE月別アーカイブ
2025年 (4)
2024年 (14)
2023年 (1)
2022年 (1)
2021年 (4)
2020年 (8)
2019年 (18)
2018年 (26)
2017年 (30)
2016年 (31)
2014年 (4)